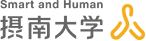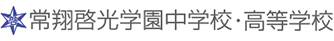インドネシアから大阪工大に留学中のリチャード・オンコさんです。高校生の時にテレビで見た「NHK学生ロボコン」の影響で日本に関心を持ち、アニメやマンガから日本語を学び日本にやってきました。インドネシアでの起業を目指し、新しい材料の半導体を研究するリチャードさんに、日本での生活や将来の目標などについて聞きました。
- Profile
-
リチャード・オンコ(Richard ONGKO)さん
1997年、インドネシアの首都、ジャカルタの西約20km に位置するタンゲラン生まれ、地元の高校を卒業後、来日。大阪文化国際学校で1年間日本語を学び、2017年、大阪工大電子情報通信工学科に入学。2021年に同大学院に進学予定。家族は父母と弟。仏教徒。
なぜ、日本への留学を決意したのですか?
高校生の時にテレビで見た「NHK学生ロボコン」がきっかけで日本にあこがれを抱くようになりました。実際に日本に来るまでには、日本のアニメやマンガなどから文化と言葉を知ることができました。また、インドネシアには日本の電化製品が多く流通しており、中国や韓国の製品と比べて壊れにくいため人気が高いです。もともとものづくりが好きで、そのような製品を自分でも作りたいと思ったことが日本への留学を決心した理由です。
インドネシアの母校では、同級生の約8割が卒業後に海外へ留学し、同じクラスの20人のうち5人が日本に留学しました。私は大学に入る前に1年間大阪市北区にある日本語学校に入学し、日本語を学びました。心斎橋のコーヒーチェーン店などでアルバイトをしながら実践的な日本語も身につけました。日本語学校で進学する大学を探していた時に、学生主体でロボット競技団体戦での上位入賞を目指して活動するロボットプロジェクトがある大阪工大のことを知り、「自分のものづくりの目標を実現できるのはここだ!」と入学を決意しました。
インドネシアの母校では、同級生の約8割が卒業後に海外へ留学し、同じクラスの20人のうち5人が日本に留学しました。私は大学に入る前に1年間大阪市北区にある日本語学校に入学し、日本語を学びました。心斎橋のコーヒーチェーン店などでアルバイトをしながら実践的な日本語も身につけました。日本語学校で進学する大学を探していた時に、学生主体でロボット競技団体戦での上位入賞を目指して活動するロボットプロジェクトがある大阪工大のことを知り、「自分のものづくりの目標を実現できるのはここだ!」と入学を決意しました。
大学4年間で打ち込んできたことを教えてください。
入学後、すぐにロボットプロジェクトに参加しました。学科を越え、たくさんの日本人の友人ができたことや、学科の授業で学んだことを実践・応用する場として活動することができたことなど、大きな財産になりました。プロジェクトでは、レスキューロボットコンテストに出場するチームに所属し、人を救い出すロボットを作りました。ソフトウエアと電子回路を担当し、救助者を傷付けない精密な動きや一部の動きを自動化するプログラムの構築など、多くのことを学ぶことができました。昨年8月に開催された「inrevium杯 第19回レスキューロボットコンテスト」では、騒音の中から救助者(人形)が発する音を正確に聞き取るため、オリジナルのノイズキャンセリングシステムを構築し、レスキュー工学大賞受賞に貢献することができました。この成果は論文にして学会発表もしました。
休みの日の楽しみはありますか?
カメラが趣味なのでコロナ禍で出歩けなくなる前は、主に自然や動物、風景を撮影してはインスタグラムに投稿していました。私は中国系インドネシア人で仏教徒ですから京都や奈良のお寺を巡るのも好きですね。コロナ禍で家にいることが多くなってからは、安い3Dプリンターを購入し、スマホケースなどを自分で設計して作っています。
日本の良いと思うところ、逆に苦手なところは何ですか?
日本の良いところは何よりも人がみな親切なところだと思います。特に会釈する文化は独特で、日本で生活する中で自然とその文化を生活習慣として身につけていたので、インドネシアに帰国した際、家族や友人から「何を意味するのか?」と聞かれたぐらいです。また、苦手なのは、マナーを気にし過ぎるところです。具体的には言葉遣いで、アニメやマン ガから基礎的な日本語を知った私にとって、日本語の“敬語”など、丁寧すぎる言葉は理解することが難しかったです。
将来の目標を教えてください。
来年進学予定の大学院修了後は、日本で半導体を取り扱う企業に就職したいと考えています。数年働いた後に帰国し、母国で半導体関連のベンチャー企業を立ち上げることが目標です。半導体はこれからのスマート社会には不可欠なものと考えるからです。インドネシアでは日本などの海外製の電化製品が多く流通しており、自国ブランドがありません。いずれは、世界に名を馳せるブランドを持つメーカーに成長させ、製品開発などで日本と対等に渡り合える国にしたいです。


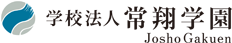









 前の記事へ
前の記事へ