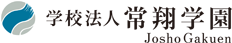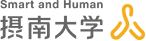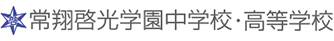大阪商工会議所 × 常翔学園 × 大阪工大
- 大阪商工会議所 会頭
- 尾崎 裕
- 学校法人常翔学園 理事長
- 久禮 哲郎
- 大阪工業大学 学長
- 西村 泰志
今年で創立140年の大阪商工会議所と、2022年に創立100年を迎える常翔学園が設置する大阪工業大学は昨年4月に連携協定を締結し、それに続いて今年4月、都心型オープンイノベーション拠点「Xport(クロスポート)」を同大梅田キャンパスに共同開設しました。大企業、中堅・中小企業、スタートアップ、社会人、学生などの多様な主体がここを拠点に社会の課題解決、新規事業創出を行うためのマッチング支援や産学連携による人材育成などのプログラムを実施していきます。大商第13代会頭は本学園の前身関西工学専修学校初代校長でもある片岡安だったというゆかりもある両者が、大阪を新たな成長拠点にするべくタッグを組んだのです。尾崎裕第26代大商会頭(大阪ガス会長)、大商議員でもある久禮哲郎本学園理事長、西村泰志大阪工大学長の3人に連携への期待、大阪のものづくりの未来などについて語り合ってもらいました。聞き手 : 西田太郎 学園本部広報室長
「ルールを与えられる」東京と「ルールを作りだす」大阪
─大阪はかつて大正期から昭和初期に「大大阪」と言われ、日本の経済の中心でした。東京一極集中から脱却し、日本の成長を牽引していくことを目指す大商ですが、大阪経済の一番の強みと弱点は何だとお考えですか?
尾崎:大阪の強みは「特色あるものづくり」「研究開発機能の集積」「アジアとの強い結びつき」の3点です。化学素材分野、一般機械、金属製品で特色あるものづくりの集積があり、医薬品・医療機器分野を始めとした企業や大学の研究開発拠点も多くあります。また、輸出入金額に占めるアジアの比率は7割を超え、それが年々増加しています。一方で、課題は国際都市としての知名度の向上ではないでしょうか。東京は“官の町”でルールが与えられる町ですが、“民の町”大阪はルールを自分で作り出してきました。新しいことを発想しやすく、まさにイノベーションにふさわしい都市です。また、外から呼び込んだ力を大きく育て、他地域に還元してきた都市です。万博などを契機にこうした開かれた魅力のある大阪の都市力を発信していきたいですね。
教員の活性化と学生の成長も
─大商は2017年度からの中期計画「たんと繁盛 大阪アクション ~最前線×最先端で、日本とアジアを牽引~」で、国内外から多様な人材や企業を引き付け、先端分野に取り組んで大阪が日本とアジアを牽引していくことを目指すと宣言しています。改めて今回の連携に最も期待するところをお話しください。
尾崎:開かれた創造的な都市という大阪の魅力を更にアップする仕掛けの一つがオープンイノベーションです。大阪・関西ではライフサイエンス産業で既にオープンイノベーションの実績がありますが、それに続くAI、IoT、ロボティクスなどの第4次産業革命分野において新たなビジネスを創出しなければなりません。これらはまさに大阪工大の得意分野の先端技術で、新たなXportの取り組みから成果が生まれることを期待しています。
久禮:ロボット市場は2020年には1兆2000億円に成長すると見られています。ロボットとともに情報系の成長分野も大阪工大が貢献できる分野です。オープンイノベーションの始まりは、アイデアはあるが資金のないベンチャーと新しい発想を求める大企業の出会う場でした。Xportではそこに“舵取り役”として大阪工大も参画し、学識のある教員と学生、大学院生が加わります。少子化による国内需要の縮小で大阪を支えてきた中小企業も海外に出ざるを得なくなっています。経済の原動力は今や国際競争力です。Xportで大阪工大はこうした固有技術を持った中小企業への専門的支援だけでなく知的財産学分野でもお手伝いができると思っています。
西村:大阪工大として期待するのは教員の研究の活性化とさまざまなプロジェクトに参加する学生の成長です。Xportでは企業が抱える実際の課題がテーマとなるので、教員の研究の幅が広がりますし、学生には在学中にビジネス創出を実体験できる場になります。私の経験では学生は企業の方の話を本当に真剣に聞きますし、接することで成長します。
尾崎:その理由は授業で学んだことが現場で実装されているのを実感できるからですね。
─大阪の中心梅田に設置されたXportを大商が推進する「大阪をイノベーションの実証事業都市に」という事業にどう生かしますか。オープンイノベーション拠点、あるいは学びの場として、梅田の利点は何だとお考えですか?
尾崎:新ビジネスを創出するキーワードは「オープンイノベーション」と「実証事業」です。社会の多様な課題にスピーディーに対応するためにはこれまでの日本企業の自前主義では追いつかず、外部と連携するオープンイノベーションが求められています。また、ものづくりのあり方も製品の原型(プロトタイプ)をすぐに実社会のフィールドで試し、その成果を研究開発にフィードバックして付加価値を向上させる実証事業という手法が注目されています。この2つを具現化できるのがXportです。また、京都と神戸の結節点にある梅田は、多様な人たちが交流し、24時間活動している刺激に満ちた街でイノベーションにふさわしい立地です。
久禮:世界の主要大学の多くは大都市にあります。大都市には人々が集まり、人々が交われば何かが生まれます。特に大阪人にはものづくりに重要なウルトラ・フレキシビリティーと言うか発想の大きな柔軟性があり、まさに梅田はXportにとって最適な場所です。
尾崎:大阪は市内に大学が少なく、やはり街の中に若者が少ないのはさびしいですね。そういう意味でも大阪工大梅田キャンパスに期待しています。
西村:既に梅田キャンパスでは2017年度から、ロボティクス&デザイン工学部の学生が正課外教育として「RDクラブ」という活動でパートナー企業の出す課題に解決策を提案する取り組みをしてきました。パートナーの企業11社にこのキャンパスまで来ていただき、127人の学生が参加しました。キャンパス内企業インターンシップです。今年度はXportの事業に取り込まれますが、参加説明会には130人以上の学生が集まり、立ち見が出るほどでした。梅田の立地を生かした教育に大きな手応えを感じています。
融合教育でライフサイエンスを担う人材を
─ライフサイエンス分野は大阪の強みのある分野ですが、製薬会社のトップも務めた久禮理事長に学園のこの分野での貢献をどう考えておられるかお聞きします。
久禮:常翔学園内には大阪工大以外に摂南大と広島国際大があり、それぞれが2020年に摂南大は農学部、広島国際大は健康スポーツ学部を設置構想中です。特に農学部は世界や日本の食、農家の高齢化などの課題に取り組みますが、ロボティクスやAIと密接した「スマート農業」と言われる分野も意識しています。農学部は薬学部、看護学部のある枚方キャンパスに計画していますが、近くには大阪工大情報科学部もあります。できれば学部、大学の壁を越えた融合教育でこれからのライフサイエンスを担える人材を育成したいです。更に同じ地域にある関西医科大、大阪歯科大と摂南大薬学部の医歯薬連携も3大学で検討しています。
尾崎:AI・ITなどを活用して日本の農業分野で技術開発を進め、サステナブルなシステムを生み出してほしいですね。
─大商は大阪を「アジアのイノベーション・ハブ」にとうたって国際戦略を展開していますが、学園と大阪工大のグローバル戦略もお聞かせください。
西村:大阪工大では学園創立100周年に向けて「教育と研究で国際連携の推進」「多文化共生キャンパスの構築」「成果の還元」の3つの柱からなるグローバル展開の基本方針を定めています。昨年度、海外へ派遣した学生は約200人、海外から受け入れた留学生は約150人で計350人にもなります。特に海外協定校の学生と混成チームを組んで英語で与えられた課題に取り組む国際PBL(課題解決型学習)には力を入れており、昨年度は計14のプログラムを実施しました。参加した学生がその後、研究活動で上位のプログラムに参加する事例も出てきており、手応えを感じています。
久禮:「国際PBLを経験すると学生は本当に成長する」と教員は口をそろえます。Xportで大商の海外ネットワークを生かし、学生、院生に海外との交流を通して、新たな発想を学んで欲しいです。海外との本気の“他流試合”で学生は鍛えられるはずです。
─大阪万博誘致へのそれぞれの取り組みと期待をお聞かせください。
尾崎:11月の開催地決定までこれからが正念場です。これまでのプロモーション活動は既に300回を超えました。「万博ステッカー・キャンペーン」を昨年10月から展開し、3月には国際博覧会事務局の調査団来日に合わせて実施した「2025万博『大阪・関西に来てや!』プロジェクト」で、千林商店街で常翔学園にご協力いただき万博誘致祈願パレード=写真=や応援セールも実施しました。万博開催の経済波及効果は全国で約2兆円と試算されています。万博は新たな技術や商品が生まれるきっかけにもなってきました。中小企業やベンチャー企業のチャレンジの場にもなります。「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマに合致した、面白いアイデアを集めて実証実験を進め、それを国内外にアピールしたいですね。2025年万博で主役となる今の学生の皆さんからも、未来を変える新技術や世界を驚かすアイデアをぜひお願いします。
西村:署名活動や「名刺サポーターキャンペーン」などにも協力しています。若者に夢を与えるイベントですから、大阪開催が決定すれば、「未来社会の実験場」である万博に大学として積極的に参加したいですね。学生の学びや教員の研究に大きな刺激となるのは間違いありません。
久禮:大阪開催が決まると大阪府との連携も生かして学園を挙げて参加したいです。特に大阪工大と摂南大の教員や学生が、パビリオン建設を始めロボット、医療分野、情報分野、都市デザインなどで貢献できるところは多いです。
─長い歴史のある大商と常翔学園ですが、次の100年をどんな100年にしたいですか。
久禮:欧米には何百年も続く名門大学が多いですが、それだけ続くためには秀でた教育・研究力と魅力的な特色が必要です。すなわち、多様性を増してレベルの向上、競争力の維持を図らなければなりません。グローバルであることが不可欠で、この2つがないとあと100年は生き残れません。そのためにオープンに世界中から優秀な人材を集めたいですね。また、常に他大学や産業界からのパートナー探しも重要になってきます。教育の質を高めて優秀な学生も集めるいい連鎖を作って行けば、ますます魅力的な学園・学校になっていくはずです。
尾崎:100年続くことは素晴らしいことですが、それがこれから100年続く保証はありません。伝統にあぐらをかかずに謙虚であるだけでなく、大商という名前は同じであっても、変化を恐れず、常に成長し進化を続けることで、その時々に求められる役割や価値を提供し続けなければなりません。都市も同じではないでしょうか。大阪という魅力ある「場」が「人」を惹き付け、そこで育った「人」がまた新たな活躍の「場」を創り出す、いわゆる“賑わいの好循環”が、大阪の発展・成長の原動力となります。この仕組みを再構築する仕掛けの一つがオープンイノベーションです。Xportなどを拠点に、新たなイノベーションに果敢に挑戦し続ける次の100年につなげていきたいと思います。



- Profile
- 尾崎 裕 大阪商工会議所会頭 兵庫県出身。東京大学工学部卒業後、1972年大阪ガス入社。2008年4月代表取締役社長。2015年4月から代表取締役会長。2015年12月から大阪商工会議所会頭。2013年6月から2015年6月に日本ガス協会会長。2017年3月から2025日本万国博覧会誘致委員会副会長。2017年6月から文楽協会理事長。